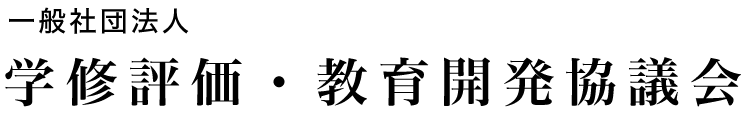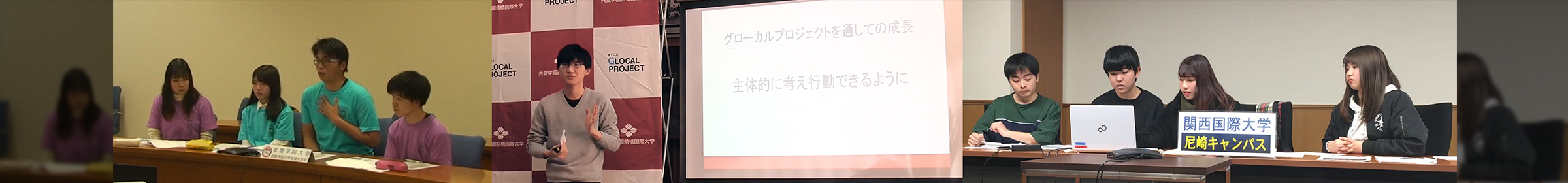
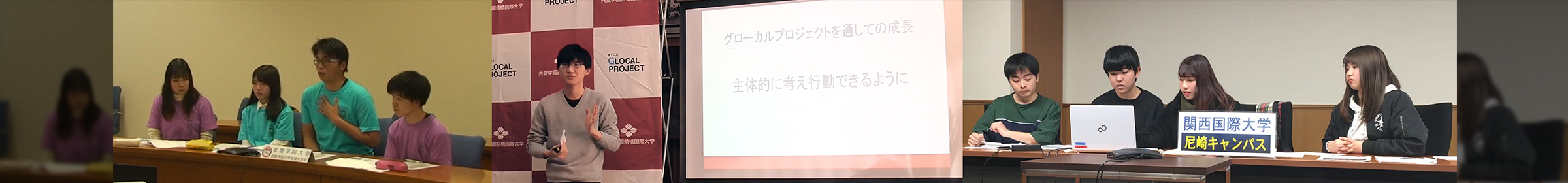
2025年度 オフキャンパス報告会
オフキャンパス報告会
2025年11月22日、KOKOPLAZA 大阪市立青少年センターにて、「オフキャンパス報告会」を実施しました。
コロナ禍を経て、今回が5回目の開催となります。テーマは「社会貢献と地域連携」。今年度は対面で開催、加盟6大学の学生チームが、ボランティアやサービスラーニング等の教室外での経験に基づいた学びについて発表し、ピア評価を行いました。
夕食の後、それぞれの取組みに対して、意見交換を行いました。活動の課題や、取組のさらなるステップアップや充実のためにどのようなことができるかなどについて、お互いにメタ的な視点で意見交換を行いました。
最後に評価の高かったチームに表彰を行いました。
今後も学生交流の一環として、また、より高次の学びにつなげる機会として、オフキャンパス報告会を継続していきます。
協賛:
株式会社 内田洋行

宮崎国際大学
「宮崎国際大学「土呂久に集まれ!」プロジェクトです。
本プロジェクトは、公害という重い歴史を背景に持つ土呂久地区を拠点として活動する、学生主体の取り組みです。
私たちは、①土呂久地区のイメージ向上、②教育学部の特性を生かした公害教育への活用、③過疎化が進む地域の活性化、という三つの目的を掲げ、継続的に活動を行っています。本プロジェクトは今年で4年目を迎え、仲間と協力しながら、日々充実した活動を続けています。
私たちが所属する宮崎国際大学には、学生の主体的な挑戦を支援する制度として「MIU学生チャレンジプロジェクト」があります。本プロジェクトは、同制度より毎年活動費のご支援をいただくことで、継続的な取り組みを実現しています。
このたびは、令和7年度オフキャンパス報告会にお招きいただき、誠にありがとうございました。本報告会への参加を通じて、多くの学びと貴重な経験を得ることができました。
今後も地域と真摯に向き合いながら、より一層充実した活動を展開してまいりたいと考えております。引き続き、ご支援とご指導を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
関西国際大学
本プログラムは、関西国際大学がグローバルスタディの一環として、フィリピン・セブ島ガース村を舞台に10年間継続してきたサービスラーニングの取り組みです。学生たちは、給食づくりや模擬授業、読み聞かせなどの活動を通して、教育環境の改善に貢献しました。
活動前にはフィリピンの歴史や言語を学び、現地ではバディと呼ばれる若者たちと協働して課題解決に取り組みました。都市部との格差や貧困の現実に直面しつつ、子どもたちの笑顔を引き出すための工夫を重ねる中で、異文化理解や英語でのコミュニケーション力、問題発見・解決力を大きく伸ばしました。
また、地域の強みを見出し、持続可能なコミュニティづくりを見据えた視点を養ったことで、社会に能動的に貢献しようとする姿勢が培われました。
参加学生にとって、学びと成長を実感できる濃密な経験となりました。
松本大学
私たち松本大学では地域連携事業を幅広く活動しています。
ゼミ活動では多岐に渡る活動があり、地元商店街の活気を取り戻すべく、松本広域連合内の魅力を発信するなど、各々目標を持ち活動しています。
ゼミ活動での地域連携以外では、学生自らが主体となって取り組む「地域づくり考房ゆめ」があり、ここでは所属学科の垣根を超え、地元の花火大会に携わる、子ども食堂の運営に参画するなどの活動をしています。
活動のなかには実施が困難なことなどもありますが、地域の魅力を伝え、地域を盛り上げるよう、継続して地域の方と一緒に取り組んでいきます。
共愛学園前橋国際大学
本学では、学生中心主義・地域との共生がモットーになっています。
特色の1つとして、Global(グローバル)とLocal(ローカル)を組み合わせたGlocal(グローカル)科目が在ります。この科目では、海外研修などで国際的視点を広げるグローバルな学びと、自治体や企業など地域社会と連携し、講義・実践的活動を行うローカルな学びを組み合わせ、学生が世界と地域を結びつけて学修することで国際的視野と地域の現状の双方を学び、講義と現場体験を通じて実践的な力を養っていきます。
また、学修を通じて育成する力として「共愛12の力」を設定しており、大学4年間の授業や正課外活動等を通して身に着けていきます。
今回発表を行った児浦ゼミは、ローカルな学びの視点から研究活動を行っています。自身の出身地であったり、興味のあるまち、愛着のあるまちなど、それぞれが自分のフィールドを設定し、その地域にある地域課題の解決に向けて提案策を講じていきます。実際にかかわってみないと見えてこない地域における良い点や、その地域の課題などがあり、座学では知りえない多くのことを学ぶことが出来ます。
新潟工科大学
「リノベラボ」プロジェクト
概要新潟工科大学と新潟大学附属長岡小学校、県内企業が連携し、小学生の発想を生かした空間づくりを実現する取り組みです。背景には、建築業界の担い手不足や既存枠組みの限界があり、次世代の担い手として小学生に注目しました。プロジェクトは、三条市の建設会社からの空き部屋活用依頼と、小学校の「ものづくり科」授業での実践希望を契機に始動。対象は長岡駅近くのWiseビル507号室(約40㎡)で、児童が提案した空間をリノベーションします。
活動はフェーズ0~7に分かれ、アイデア提案、模型制作、発表会、詳細設計、クラウドファンディングなどを実施。学習発表会で選ばれた「心おどる秘密基地」と「誰でも使える音楽スペース」を基に、児童は大学院生や企業と協働し、費用試算や運営方法まで検討しました。クラウドファンディングでは約170万円を集め、1部屋の改修を決定。最終的に音楽スペース案が採用され、壁材や床材の選定、返礼品制作なども児童が主体的に行っています。
本プロジェクトは、創造性や協働力を育む教育効果を示すとともに、地域・学校・企業が連携する新しい学びのモデルとして、社会的価値を創出しました。今後は施工完了とお披露目会を予定し、完成後の影響調査や教育現場への還元が課題です。
札幌国際大学
この発表では、今後訪れる2040年問題を見据え、メタバースやVR、AIなどのIT技術を活用した新しい支援の形を提案するとともに、生きづらさを抱える子どもや若者にとって、メタバースや現実に近い安心感をもてる「もう一つの日常」になり得るのではないかという提案をするものであり、実際の通信制高校や大学での実践、フリースクール等の従来の支援の事例を遠し、時代の変化に対応した多様な居場所づくりの重要さについてお話ししました。